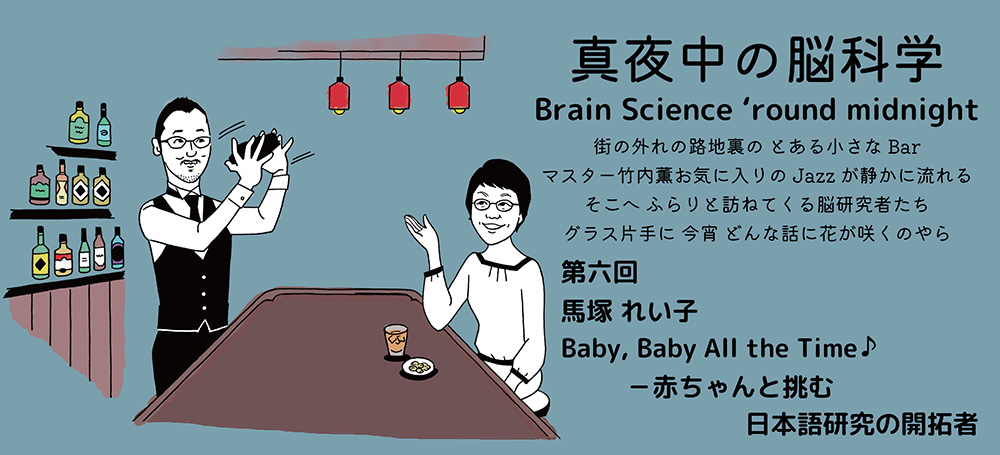

第六回 馬塚れい子
Baby, Baby All the Time♪-赤ちゃんと挑む 日本語研究の開拓者 前編
心理学でもあり脳科学でもある「言語発達」の研究
竹内 馬塚さんは赤ちゃんと言葉について研究されていると聞きました。
馬塚 そうなんです。私が率いる言語発達研究チームでは“赤ちゃん研究”と呼んでいます。これまでの研究で、発話する前、つまり単語や文が口から出てくる前の赤ちゃんのときから、すでに言語についての学びは起動しているということが分かってきました。そこで、赤ちゃんや幼少期の小さな子どもを主な対象として、どのように発話前後に言語発達の基礎を学習しているのか、言語発達のメカニズムを研究しています。
竹内 それは「日本語獲得のプロセス」ということですか?
馬塚 そうです。私の経歴を少しお話すると、理研で現在のラボを立ち上げる前は15年ほど米国ノースカロライナ州にあるデューク大学で、心理学を教えながら言語の発達を研究していました。そのころまでにも言語発達に関する研究論文はたくさん報告されているのですが、その大多数は英語を対象にしているんですね。それに加えてフランス語、ドイツ語、オランダ語などが英語との比較研究として報告されている。日本語などアジアの言語についてはほとんど研究対象になっていなかった。私は静岡県生まれの日本語ネイティブスピーカーなので、「英語をフランス語やドイツ語と比べてこれが分かった、だからこれが言語獲得のメカニズムだ」と言われても、どうしても違和感があるわけですよね。今こうして話している日本語って、英語とは違った特性をいろいろ持っているわけで、欧米の言語で分かったことをそのまま日本語の発達に当てはめることはできないんじゃないか、と考えたのがきっかけです。
竹内 そうそう、例えばスペイン語とイタリア語って似ているな、などと思いますが、日本語って英語と比較すると音も文法も全然違いますよね。僕も父親の仕事の関係で幼少期にアメリカで数年間暮らしていたんですが、二つの言語の違いについては身をもって体験しました。
馬塚 そう、全然違いますよね。日本語ネイティブスピーカーとして言語発達の研究で自分が一番貢献できるのは「日本語を一番初めに学ぶ“赤ちゃん”を見る研究じゃないか」と考えたわけです。
竹内 ある意味、日本語を母国語とする人にしかできない研究とも言えますね。
馬塚 そうです。そういうことを米国で考えていた15年ほど前、理研で「脳を育てる」という新しいプロジェクトができたのを知り、帰国してラボを立ち上げました。
竹内 言語発達というと、心理学の領域になるんですか? 言葉ですからもちろん脳も関わっている。赤ちゃんなので発達心理学的な分野でもありそうだし、ソシュールやチョムスキーなど言語研究で著名な学者の仕事は言語学や哲学的な分野ですし……振り分けが難しい気もします。
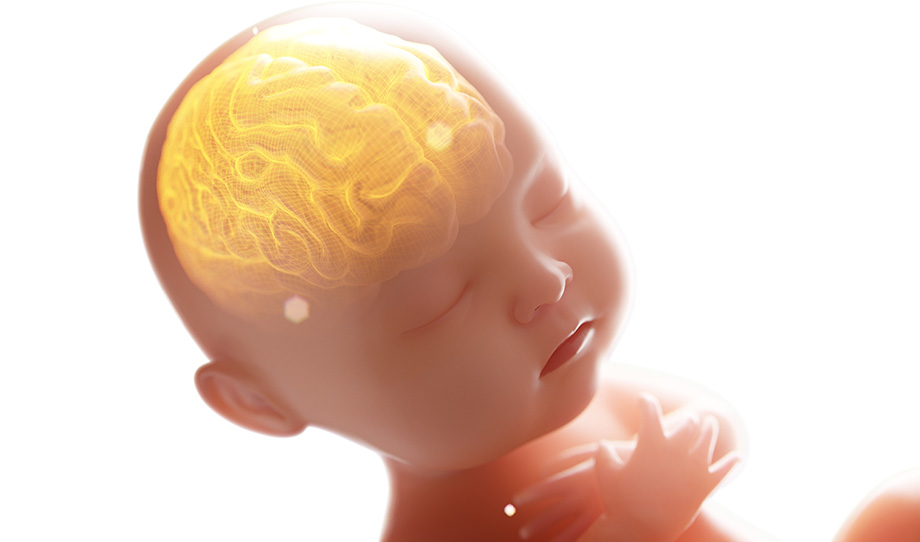
馬塚 心理学であり脳科学でもあると思います。私が所属している脳神経科学研究センターは、もちろん脳を研究する場所でして、ここに所属するラボの多くが行っている記憶や脳疾患の仕組みを分子や細胞、神経回路、行動などのレベルで調べていく研究をいわゆる脳科学のスタンダードと呼ぶとすれば、言語発達研究はスタンダードから外れているとは思います。しかし、理研に応募した際に「赤ちゃんラボを作って言語発達の研究をしたい」と、当時、センター長であった甘利俊一先生や特別顧問の伊藤正男先生に相談したら、「大丈夫です。赤ちゃんも脳を持っていますから!」と、とても太っ腹なことを言ってくださった。
竹内 その通りですね。脳科学としての言語発達研究の意義を理解いただけたんですね。
「日本語の言語発達」研究を切り拓く
馬塚 はい、全面サポートをいただきました。ラボを立ち上げた当時、乳児を対象とした言語発達という研究分野は日本でも存在してはいたのですが、参画している研究者はごく少数で、主に発達心理学の人々が関わっていた。実は、日本の心理学という学問の規模は世界と比べるとすごく小さいんです。例えば米国デューク大学の場合は、学部への新入生約650人のうちダブルメジャーも含め心理学メジャーで卒業する学生は100人以上いる。
竹内 そんなにたくさんですか!
馬塚 はい。この割合はアメリカ全土の大学で共通しています。デューク大学の場合は、学生が一番多い専攻が経済学、2番目が心理学です。学生が多ければ、もちろん指導する教員、研究者も多くなる。学生が一学年600人として、心理学の教員は30~40人規模でいます。もっと大きな州立大学の場合には、発達心理学だけで教員は30人、認知心理学で30人、全部で100人ぐらいの規模になる。ところが例えば私の母校である名古屋大学では、もうずいぶんと昔の話にはなるんですが、当時の一学年が2000人弱で、そのうち私が所属していた文学部哲学科心理学の定員は6名ぐらいだったと思います。教育学部にも教育心理学という専攻がありましたが、そことあわせても20名ほどでした。
竹内 比較するとかなり少ないですね。そうすると言語発達を研究している人数も必然的に少なくなる。
馬塚 そうなりますよね。日本の大学で心理学を教えていらっしゃる先生方が赤ちゃんの言語獲得を研究しようと思っても、場所や実験機材、人材を含め、なかなかリソースが周りにない。最近ではすごくクリエイティブな研究者も増えてきて日本でも赤ちゃん研究がだいぶん発展してはきたのですが、やっぱり欧米の大学とは規模が全然違う。
竹内 馬塚さんは黎明期と言えるなかで、日本語の言語発達研究を開始されたんですね。
馬塚 ラボを立ち上げた当初は試行錯誤の繰り返しで、研究をしっかり動かせるようになるまでに5年ほどかかりました。もちろん日本の大学では乳児を対象とした実験的な研究の経験のある学生は少ないので、大学院で赤ちゃん実験を経験していなくても「とりあえず面白そうだな」と来てくれる人たちをラボメンバーとしてまず採用しました。赤ちゃんの行動実験や脳波測定などの研究手法を2週間から1カ月の間にできるだけ学んできてくださいと、海外のラボに送り込むことから始めました。国内で赤ちゃん研究を進めていた研究室にもスタッフを派遣して、研究対象となる赤ちゃんたちをどうやってリクルートするかも学ばせてもらいました。
竹内 ほんとうにゼロからはじめるスタートアップ企業の成長みたいな感じですね。
馬塚 苦労ももちろん多くありましたが、英語などの欧米言語で確認されている基礎的な知見に関して、日本語の場合はどうなのかと比較検証を少しずつこつこつ積み上げながら、10年ほどである程度、日本語と英語の言語習得の相違点が分かってきました。
言葉の数だけ研究がある
竹内 現在、日本語からさらに広げたとても面白そうなプロジェクトを進めていると聞きました。
馬塚 アジア欧米言語獲得研究プロジェクトという多国間研究です。実際にはこのプロジェクトは2016年から始動していて、2020年に継続・拡大するために特別推進課題として研究費を獲得しました。このプロジェクトでは日本語のみならずアジア諸国の異なる言語の発達プロセスを研究しています。以前の研究から日本語と英語との相違点は見えてきてはいたのですが、「日本語が特殊なのか? それとも英語が特殊なのか?」って実のところ測りようがないですよね。今までは英語と欧米諸国言語との比較研究が中心だったのを、今度はアジア諸国言語でも比較研究を推進し、さらにはその結果を欧米諸国言語とも比較できるように、基盤を作っていこうとしています。

竹内 言語に関する研究は少し特殊な事情がありそうですね。同じ脳機能などを調べるにしても、研究対象それぞれの母国語、暮らしている環境、文化的背景までも含まないと比較検証できない。
馬塚 そうなんです。例えば理研でヒトの脳と記憶について研究して報告した場合、理研が日本にあるからといって「日本語を母国語とするヒトを対象にした記憶の研究成果は、日本語を母国語としないヒトの脳には当てはめられない」と批判されることはないですよね。でも、それが言語の研究となると「言語研究のスタンダード=英語での研究」という考え方が歴史的にどっかりと横たわっている。ひるがえせば、私たちの研究もいつまでも「日本語と英語の比較」にとらわれていてはいけないわけです。アジアにだってさまざまな言語があって、それぞれに研究すべき特徴があるわけですから。
竹内 なるほど。実際にはどうやってアジア諸国に高度に専門的な研究ができるラボを作っていくんですか? ラボをスタートさせた時とは反対に、馬塚さんらノウハウを持つ研究者が各国を行脚して、現地で研究者をリクルートして、リソースを共有し方法をトレーニングして、というのも面白そうですが時間がかかっちゃいますよね。
馬塚 実はそれに近いことをしています! 例えば、デューク大学での教え子の一人が卒業後に母国の韓国に戻り、今、大学で発達心理学を教えていて、赤ちゃん研究に興味はあるけれども研究室を立ち上げるためのリソースがない。そこで私たちが基礎的なインフラをバックアップするのでやってみないか、と聞いてみたところ「ぜひやりたい」という返事でした。これと似たような話がタイのタマサート大学、香港の香港大学(香港大学との共同研究は2018年で終了、2020年からシンガポール国立大学が新規参加)であり、各国の若手研究者たちを巻き込んでプロジェクトがスタートすることになりました。人材育成の面でも、まずは私たちのラボに来てもらい、赤ちゃん実験やデータ解析のやり方、被験者である赤ちゃんのリクルート方法などを2カ月ほどで習得してもらいます。その方たちがそれぞれのラボに戻る際にこちらのスタッフが一緒について行って実験のセットアップを手伝う、ということをしながら4カ国での比較研究をスタートさせました。面白い結果も少しずつ出てきていて、アジアの国々での言語発達の共通性が見えてきました。
赤ちゃん研究から見えてきた、脳の言語処理機能
竹内 アジアではこういう傾向がある、ヨーロッパではこういう傾向がある、ということですか?
馬塚 そうなんです。お母さん、お父さんが赤ちゃんに話しかける言葉というのが、赤ちゃんの言語発達においての初めの入力なわけですよね。そこに違いが見えてきました。日本では、当たり前すぎてあまり意識していないと思いますが、大人が赤ちゃんに話し掛けるときに、大人同士とはちょっと違う話し方をしますよね。この話し方、IDS(インファント・ダイレクテッド・スピーチ)とちゃんと名称があるんですよ。
竹内 赤ちゃんに話しかけるときに「はーい、パパでちゅよ」とか言う、いわゆる赤ちゃん言葉ということですか?
馬塚 実は「パパでちゅよ」はちょっと違うんです。赤ちゃんに対して大人がこういう感じで話しているというイメージはあるのですが、実際に自分の赤ちゃんにいつもそう話しかけているお父さんって、ほとんどいないんです。
竹内 言われてみればたしかに。じゃあ、車のことを「ブーブー」とかいうのは?
馬塚 それです! ご飯のことを「まんま」、歩くことを「あんよ」、寝ることを「ねんね」とか言いますよね。私も含めて、こういう語彙について研究している研究者の間では「育児語彙:インファント・ダイレクテッド・ボキャブラリー」と呼んでいまして、これにも言語差、あるんです。そして、日本語や韓国語ではそういう語彙が非常に多いことが分かりました。実はこれって特殊なケースで、英語の場合には、大人になって使用する単語とは全く違う単語を子どもだけに使う、というのは非常に少ないんです。
竹内 英語だと小さな子どもにはおしっこのことを「ピピ」と言ったり、うんちのことを「プープー」って言ったりはしますよね。
馬塚 そうですね。それは大人の会話では出てこない語彙ですよね。あと英語圏では小さい時にお母さん、お父さんに対して「マミー」「ダディー」と言いますけれど、成長してから使う「マム」や「ダッド」からかけ離れてはいない。車を「ブーブー」に置き換えてしまうのとは全然違いますよね。英語では、育児語彙はあくまでも将来学ぶべき単語からのちょっとした変形なので、大人で使う語彙を学ぶ手助けになっている、と言われてきました。しかし日本語の場合、お風呂を「チャプチャプ」や、犬を「ワンワン」と呼んでいて、あとですっかり学び直さないといけないですよね。
竹内 そもそも何のために、日本語では合理的ではない方法でやっているんですかね。
馬塚 まず、赤ちゃんはそういう単語が出てくると、そこにパッと注意がいくんです。大好きなんですよ。「まんま、ワンワン、ブーブー」と言えば、こっちを見て聞いてくれる。親がそういう単語を使って、赤ちゃんも覚えて使うようになる。一時的ではあってもコミュニケーションの方法として役に立っている。ちょうど、自転車の補助車輪みたいな役割でしょうか。いきなり自転車に乗るのも難しいから、後のち乗れるようになるための必要なステップのような機能となっている。
竹内 それはそれで合理的な方法ではある。
馬塚 英語中心の言語発達研究では、英語のマミーやダディーといった形が例となって「子どもが将来英語を学ぶのに役に立つから、大人で使うマム、ダッドの特徴を強調したような形でマミー、ダディーと呼ぶ」という議論がメインになって、インファント・ダイレクテッド・スピーチの機能的意味が語られていたわけです。しかし、日本語を見てみると、ワンワンとかブーブーは犬と車とは全く異なる、学びとしては二度手間になっている。そうなると英語を対象とした研究で言われていたこととはちょっと話が違うぞ、ということが見えてくるわけです。

竹内 それぞれの言語での違いは比較することで見えてきた。では反対に、いかなる言語の場合でも共通している、人間の脳が言語を獲得する際の不変的なシステムみたいなものは少しずつ見えてきているのでしょうか?
馬塚 はい。少しずつですが、見えてきたことはあります。例えば、言語の処理は脳の左半球が優位に働いていると言われていています。言語処理に関わるブローカ野とかウェルニッケ野のような脳領域は左半球にあります。これを利用して、赤ちゃんが音声を聞いているときの脳活動を計測し、赤ちゃんが人の声のさまざまな特性を「言語」として認識するようになる過程を調べる研究が進んでいます。
竹内 ただの音なのか、それとも意味をもつ言葉なのか、いつからちゃんと識別できているかを観察するわけですね?
馬塚 そうです。私のラボから2013年に報告した研究なのですが、日本語の多くの方言には「雨」と「飴」のようにカナで書くと同じ「あめ」という単語なのに、音の高さで区別するピッチアクセントという語彙レベルの韻律があります。関東と関西ではアクセントの位置が違う場合もあるので、同じエリアで育っている赤ちゃんを対象にします。この実験では東京近辺で育っている4カ月と10カ月齢の赤ちゃんを対象に、カナで書くと同じだけれども「雨・亀・錐(あめ・かめ・きり)」などのような「高低」ピッチアクセントをもつ単語と、「飴、瓶、霧」のような「低高」のピッチアクセントを持ち意味の異なる単語を繰り返し聞かせ、脳活動を調べたんです。どちらの月齢でも「高低」なのか「低高」なのかを聞き分けてはいるのですが、10カ月の赤ちゃんだけに脳の左半球に優位な活動が観察されました。これは、赤ちゃんが4カ月から10カ月に成長する間に、ピッチアクセントが自分の母語の特性だと学習して、脳が「言語の音声」として処理するようになったことを示しています。
竹内 それは知性の表れですよね。外界の“音”という入力を手掛かりに、脳内の回路がつながり、そこに意味を加えていけるようになる第一段階ということですね。
馬塚 実は聴覚情報だけではないんです。私たちの研究ではありませんが、先天的なろうで手話を母語としているヒトの脳では、視覚情報として入力された手話が音声言語と同じ言語野で処理されるようになることも知られています。もともと脳には、言語のような複雑で高速の情報処理を担うに適したネットワークがあるのですが、乳幼児が環境音の中から、これはヒトの音声だ、これは自分に向けられた音声だ、これはこの言語の特徴だ、という風に少しずつ母語を学んでいくにつれ、母語の音声はネットワークで効率的に処理されるようになり、さらに言語の獲得を促進させるというサイクルで進んでいくのではないかと考えられています。
完全なバイリンガルは、ほぼあり得ない
竹内 英語をはじめ外国語の習得って、永遠の課題というか、子どもから大人まで多くの人が学校や英会話スクールなどで取り組んでいますよね。その習得具合やテストのスコアなどが進学や就職の際の評価にも直結したりするから、結構一生懸命やる。大人が学び直す際には「あ~、もっと早くからやっておけば」と思う方もたくさんいると思います。また、自分が苦労している分、子どもには小さいうちからバイリンガル教育をさせたいという親も多いのではないでしょうか。僕自身が小学校3年生から5年生の間、ニューヨークの現地校に入っていた経験もあり、バイリンガル教育をする小学校を経営しているんです。そこで第二言語として英語を小学生に教えていると、いろいろな気づきがあります。今では超早期教育として、赤ちゃんのころから英語を聞かせる、なんて教材もあったりしますけれど、言語発達研究の視点で言うと100パーセントのバイリンガルってあり得るんでしょうか?

馬塚 実は、小さいときから二カ国語を話す子どもであったとしても、完全なバイリンガルってほぼあり得ないんです。必ずどちらかの言語がドミナント(第一言語)になって思考したり会話したりしています。最初はやはり、一番近くで一番長い時間を一緒に過ごす母親が話す言語が第一言語となる場合が多くなります。例えば、日本人の夫婦が乳児を連れてアメリカに転勤したとする。はじめは家で親と日本語で話しているので日本語が第一言語になりますが、そのうち保育園に行き始めて周りの子どもたちがみな英語で会話していれば、知らないうちに英語がだんだんドミナントになっていきます。学校に行って英語で勉強してテレビも読む本も英語になっていき、それが続くと英語が第一言語だけれども日本語も話せるバイリンガルになります。
竹内 誰にとっても第一言語というものがあり、その言語は環境やそこにいる期間などで、ほかの言語に置き換わっちゃうのですね。
馬塚 はい。何をもって母語と定義するか、という話にもなりますが、意外と流動的なんです。2003年にフランス人研究者のピリエたちが報告したこんな研究があります。朝鮮戦争が終わった1953年ごろ、韓国の5歳から7歳くらいの子どもたちが経済的な事情などでフランスを中心とした国々へ養子として受け入れられたことがありました。彼らは韓国にいる産みの親や親せきから完全に切り離され、フランスへ渡ってからはフランス語だけで生活したために、大人になってフランス語しか分からない状態です。とはいえ彼らはフランスに来る前は少なくとも5~7年ほどは韓国で韓国語しか知らずに暮らしていたわけですから、彼らのなかに何かしらの韓国語の痕跡が残っているのではといろいろ調べました。その結果は、少なくともこの研究においては、韓国語のインプットが全くない状態でフランス語だけで育つと、もうすっかりフランス語で上書きされていて、かつて母語であった韓国語の痕跡は全く出てこなかった。
竹内 うわ~。そんなに跡形もなく消えてしまう。
馬塚 この研究では、韓国出身でフランス育ちの彼らにとって同じく知らない言語であるポーランド語とフランス語を比べた脳波と、韓国語とフランス語を比べた脳波の二つを観察すると全く差がなかった。もちろん、自分が韓国からフランスに養子として来たというのは理解しているのですが、自分が韓国にいた頃に韓国語を話していたという意識も記憶も全くないそうです。さらに複雑なことを被験者にやってもらい測定すれば、彼らの脳のどこかに韓国語の記憶の痕跡はあるんじゃないか、と主張する研究者もいますが、言語に関してはある程度メンテナンスしていないと、特に小さい頃に学んだ言語というのはその言語に触れる機会がなくなったとたん、どんどんほかの言語に侵食されていく、と報告しています。
二つめ、三つめの言語獲得
竹内 それって脳が学習できる期間といわれる臨界期にも関係するのですか? 言語発達の臨界期は幼児期にあると言われているようですから、5~7歳だとまだ臨界期を迎えていなかった、ということではないでしょうか。例えば10歳とか13歳とかで養子として母国以外で暮らしはじめた場合、韓国語がそのままドミナント、つまり母語となるのかなって。
馬塚 実は、言語獲得の臨界期ってそんなにクリアにいつからまでという期間があるわけではないんですよね。韓国からアメリカに移民した人たちを大規模に調査した研究では、母音や子音の発音が母語話者のようにできるようになるのは5歳ぐらいまでに移民した人だろうという結果がでました。でも同じ調査をスペイン語を母語とする移民を対象に実施してみたら、16歳で移民した人でも英語の母語話者と区別がつかないような発音ができるということが分かりました。これは、ネイティブ同等の発音ができるかどうかは年齢だけでなく、各言語の特性によっても大きく変わってくるということを示しています。文法の獲得は発音の獲得よりも臨界期が遅いとも言われていますが、これも母語と新しい言語がどのぐらい共通した特性を持つかで大きく変わってくることも知られています。
竹内 なるほど。言語それぞれの特徴や第一言語と似ているか違うかも大きく影響するのですね。
馬塚 そうですね。現在の地球上では母国語のみを使用するモノリンガルで過ごせてしまう人はものすごく少ないんですよね。日常的に二つ、三つの言語を話すバイリンガル、トリリンガルの人たちの方が多いんですよ。言語を二つ以上学ぶこと自体はあまり問題ではない。しかし、まれにあることなのですが、バイリンガルではなくてサブリンガル(またはセミリンガルやダブルリミテッド)という状態があるんです。例えばメキシコで貧しい生活をしていた家族がアメリカに移民としてやってくる。カリフォルニアの大きな農場などで、野菜や果物を摘み取るような仕事をする。そうすると、作物の収穫時期に合わせて今月はこの辺で、翌月はこの辺で働くという具合に収穫に合わせて移動するわけです。そうなると子どもたちは親が仕事で移動するごとに学校を転校するので、英語もほとんど身につかない。家では親が使用しているスペイン語のみ話す。しかし子どもたちはスペイン語での教育もちゃんと受けていないので、メキシコに戻って会社で仕事ができるほどのスペイン語運用能力があるかと言われれば、そうはならない。つまり、母語のスペイン語も移住先の英語も、どちらも中途半端なレベルでしか獲得できない、という状態になってしまうわけです。

竹内 本人にとっては仕事の選択肢が限られてしまうし、アイデンティティにも影響が出そうです。
馬塚 こうした移民のケースのように学びに関するリソースが限られている場合には、両方の言語をやるよりは全力を挙げてスペイン語だけ、または英語だけに力を注ぐ方が将来的にはメリットがあるかもしれない。しかし二カ国語を学ぶことが本質的に害になるわけでもない。例えばバイリンガルになった結果、英語と日本語の両方とも70パーセント程できるとしたら、その人の総合的な言語能力としては、あわせて140パーセントと言ってもいいじゃないですか。それを100パーセントできる言語がない、とネガティブと考えるか、いや、英語もできるから140パーセントと捉えるかは、その人の価値観や言語の活かし方次第となってくる。そこはもう本人の選択なんだと思います。
Profile
-

-
今夜の研究者
馬塚 れい子(まづか れいこ)
理化学研究所 脳神経科学研究センターにて言語発達研究チームを率いる。
静岡県浜松市出身。名古屋大学大学院心理学部修了後、イギリス、エジンバラ大学で言語学の修士を取得。その後渡米しコーネル大学にて博士課程修了(発達心理学)。
デューク大学の準教授教授を経て2004年より現職。若いころは読書が趣味で、雑誌や漫画、小説など手あたり次第に読んでいたが、最近はだらだらと何もしないですごすことが贅沢な趣味になってきた。研究以外の時間はアメリカ在住の夫とオンラインで長話をしたり、たまに散歩に出かけたりするのを楽しんでいる。
-

-
Barのマスター
竹内 薫
猫好きサイエンス作家。理学博士。科学評論、エッセイ、書評、テレビ・ラジオ出演、講演などを精力的にこなす。AI時代を生き抜くための教育を実践する、YESインターナショナルスクール校長。
X(Twitter): @7takeuchi7
Topイラスト
ツグヲ・ホン多(asterisk-agency)
編集協力



